DX 100
1983年に発売されたYAMAHA社のDX 7は、6オペレータの32アルゴリズムを備えたフルデジタルのシンセサイザーで、アナログのシンセサイザーでは難しかったFM(フリケンシー・モジュレーション)音源によるキラキラした音色、同時発音数16、MIDI装備、音色メモリも備えて248,000円と言う当時としては画期的な仕様により爆発的にヒットし、YAMAHA DX 7の登場によってシンセサイザーの主流だったアナログのシンセサイザーは市場から消えて行きました。
その後、1985年にFMシンセサイザーの入門機として定価69,800円で発売されたのがDX 100です。当時は、ミニ鍵盤で乾電池駆動も可能なことからショルダーキーボードとして使用する人が多く、メインのキーボードとして使用されることは少なかったと思います。90年代に入ると、Roger TroutmanはTalkbox用にMinimoogからDX 100へ移行しています。Roger Troutmanが使用していることから、TalkboxerはDX 100を使用しているケースがほとんどで、これが影響しているのか分かりませんが中古市場で現在も高値で取引されています。
TX81Z等も基本概念は同じ
DX 100と同じアルゴリズム/機能性を備えた製品は、他にもDX21、DX27、DX27S、SDX27S、TX81Z等でDX 100で作れる音色はこれらの製品でも作ることができます。但し全ての製品に同じD/Aコンバータが搭載されているかは分かりませんので、同じパラメーターでも出音が微妙に異なる場合もあるかも知れません。
FM音源での音作り
FM音源での音作りは、アナログシンセサイザーと比べて結果を予想しにくい方式と言えますが、DX 100では分かりやすい様にオペレータと言う仮想のオシレータの様な物が4個用意されており、このオペレータを直列/並列で接続し音色を作ります。各オペレータは、キャリア(音程、音量)とモジュレータ(音色)と呼ばれ役割が決まっており、各オペレータの組み合わせをアルゴリズムと言います。DX 100は8種類のアルゴリズムが用意されているので、キャリアとモジュレータを様々な組み合わせで使用することができます。全てのオペレータが並列のアルゴリズムの場合には一般的な加算合成方式になり、オペレータが直列接続されている場合にはFM(周波数変調)音源になるのです。
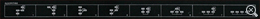
DX 100のアルゴリズム